三田 真由(さんだ まゆ)
TOSAKANMURI FOODS主宰
フードクリエーター・パン職人
(1999年[1998年度]大学院造形研究科 デザイン専攻 空間演出デザインコース修了)
和歌山県(海)生まれ、京都府南部(山)育ち。
ファッションデザイナーに憧れて武蔵野美術大学空間演出デザイン学科に入学するも、ファッションより「モノの命」について考える日々を送る。大学院修了後、数年を経て、自らがつくり出したモノへの最大の供養は、それらを食べてしまうことなのではないかと気がつき、「食を通したモノづくりと表現」を目標にかかげる。「食」の技術を身につけるべく、パン屋にて5年間修業。2006年より、「食」にまつわることを様々に展開するTOSAKANMURI FOODSを始動。2009年三鷹にて「パン屋 tOki dOki」をはじめる。2017年西荻窪に移転。「モノの命」についてはずっと考え中。
WEBサイト:TOSAKANMURI FOODS
Instagram:@tokidoki_tosakanmuri
【スライド写真について】
1. 本人ポートレイト
2. 立花文穂さんの作品にちなんだ『福笑いクッキー』
3. 三田さんが作るパン
4. 『にじのサンドイッチ』
5. 在学中のポートフォリオ
モノの命を伝えるため。食を通した表現活動
─ ムサビを選んだきっかけは?
高校は京都府立城南高校(現:京都府立城南菱創高等学校)の、理系クラスだったんです。だから美大に進学する人はほとんどいなくて、担任の先生からは「ぼくも専門外なので、好きにやりなさい」と。ただ、絵を描くのが楽しすぎて、途中で「そんなに行かなきゃだめなの?」と確認されるほど予備校に通いました(笑)。
ムサビを知ったのは、3つ上の兄が考えていた進路を通じてです。中学3年生だったわたしは「なんて楽しそうな大学があるんだ、東京に行くぞ」と決めました。服や布など、テキスタイルを学びたいなという気持ちの一方で、コピーライターのお仕事も面白そうだなとも思っていて。そんな時に、小池一子先生(現:武蔵野美術大学名誉教授)がファッションコースで教鞭を執っているということがわかり、進路をしぼりました。

─ ムサビで夢中になったことを教えてください。
上京したての1、2年生は、いろんなものを吸収する時期という感じでした。友だちができて、「こんなのがあるよ」と聞いては、映画館に行ったり、ライブに行ったり。課題がある時はたいてい遅くまで学校に残って制作していました。教室にCDラジカセを持ってきて、制作中はみんなで好きな曲をかけたりして。
ただ、当時、グループでの活動があまり得意ではなくて。そんな時、大先輩のみうらじゅんさん(視覚伝達デザイン学科卒業)の『アイデン&ティティ(1992, 青林堂)』という漫画を読んだんです。その中に出てくる、『君の立場からすれば君は正しい。僕の立場からすれば僕は正しい』というボブ・ディランの言葉に、みんなそれぞれ自分の意見や考えがあるんだなと、助けられました。

卒業制作は、12号館下の学食から敢えて見える場所に展示した『対 気分 〜さんま定食の場合〜』。3メートルにも及ぶ大作は、ご飯や秋刀魚の中に入ることができる。「『物も者もモノ』を根底に、相手の立場について考えた時、その相手(対象)は食べものでした。それで、秋刀魚定食の気持ちになってみようと思いました」
─ 在学中は、どのようなテーマで制作をされていましたか?
幼少期から抱いていた感覚が原点です。幼稚園から帰ると、当時飼っていたニワトリにはもちろん、花や植木やぬいぐるみなど、家の中のあらゆる物に、まず挨拶をしていました。処分しなくてはならないくらい短くなった鉛筆には「ごめんね」と言いながら、ゴミ箱に入れたりしていて。「あれ、物にも命があるぞ」と気づいてからは、「物と者」の境目がだんだんとわからなくなってしまったんです。
学生時代は、「モノの命」について伝えるために作ったのに、展示が終わると粗大ゴミにしかならない作品ばかりで(笑)、「これは矛盾しているぞ」と感じ始めました。

幼少期の三田さん。大切そうに抱いているのがTOSAKANMURI FOODS(トサカンムリフーズ)の「とさか」のモデルとなったヒヨ太郎さん。
─ その気づきと共に大学を卒業し、その後はどう過ごされたのでしょうか。
大学院卒業後は1度、舞台の小道具を作る工房で働きましたが、モノの命への葛藤は消えず、色々と考えるうちに、自分が作り出したモノへの最大の供養は、それらを食べることだなと思うようになりました。だったら、その(この先、自分が作る)食べものに失礼にならないように、しっかりと技術を身につけようと考えたんです。それで、思いついたのがパンでした。そのためにまずは「働きたい」と思えるパン屋さんを見つけることにしました。
当時、ちょうどいろんなタイプのパン屋さんができ始めていた頃で、都内にあるパン屋さんを巡って、食パンを買っては、すぐにお店の外で食べてみたりして。「ここ」と決めたお店に電話をして、なんとか面接にこぎつけて。「とりあえず来てみる?」と言われたので、次の日の早朝から働かせてもらうことにしました。この機会を逃しちゃいけない、と。
製パン学校も出ていないし、はじめは、できないことも多く、悔しい思いもしました。でもある時、パン作りはデッサンに似ているなって気がついたんです。レシピはあるけれど、気温や湿度、その日の様子を見ながら作っていく。パン作りは私にとって、今でも物作りの基本だと思っています。
数年経ち、そろそろ自分の制作もしたいと考え始めていた頃、アパレル業界の知り合いに「ケータリングからやってみたら?」と声をかけていただきました。パンをはじめとして、サンドイッチやキッシュ、焼き菓子やお惣菜など、パン屋さんで学んだことがとても役に立ったんです。

─ 現在はTOSAKANMURI FOODS(トサカンムリフーズ)としてパン屋 tOki dOki(ときどき)やフードコーディネート、執筆業など食にまつわるさまざまなお仕事をされています。料理という枠を超えた表現活動は、どのようなきっかけがあったのでしょうか。
料理家で文筆家の高山なおみさんが、映画『ホノカアボーイ(2009)』で、料理を担当するということで、ハワイでの撮影にアシスタントとして誘っていただいたんです。高山さんも含め、ケータリングなど様々な場で出会った方たちとのつながりや、第一線で活躍しながら、遊ぶ時も全力な大人たちに会えたことも、お仕事やプライベートにずいぶん影響していると思います。
自分の活動として、いちばん大きかったのは、通販カタログ『haco.(フェリシモ出版)』さんからのご依頼です。作品として料理制作からスタイリングまでやらせていただいて、それにまつわる小さな物語も書いていました。
思い返すと、ファッションコースの授業では、幅広くいろんなことを学んだと思います。課題では、作品の制作と同じくらい時間をかけてポートフォリオを作ることもあって、「コンセプトを大事にしなさい」と教えられてきたような気がしているんです。この『haco.』さんでの制作もその教えがすごく生かされたと思うし、今も何か作る時にはまずはよく考えます。自分の中で納得して作ったものは、命の宿り方が違うような気がしています。作品に文章を添える場合は、文章に頼りすぎていないか? と、いつも自問自答しながら書いていますが。

『haco.』の連載で発表した『太陽のおっちゃん』
─ 現在TOSAKANMURI FOODSでは、どのような活動をされていますか?
本職が自分でもわからなくて。でも、パン屋さんと言われることが多いです。最近は、パン屋の隣のスペースをギャラリーとして使うことも。他には、友人のライブに合わせてフードを作ったり。カフェや野外広場などで移動映画館をしているKino Iglu(キノ・イグルー)さんとは、もう10年以上、毎年冬に横須賀美術館で映画の上映イベントをしていて、彼らがセレクトした映画にちなんだフードを、私が作っています。
そして、パン屋 tOki dOki のパンはお客様の暮らしに、そっと溶け込めるような、日常のパンを作りたいと思っていて。お客様とお話しするだけでも、本当にホッとするんです。一緒にご来店してくれるワンちゃんには「今日も食パンみたいに、こんがりいい色だね〜」なんて声かけたりしています(笑)。
他にも面白いお仕事いただけたら、いろんなことをしてみたいです。

ムサビの卒業生でもある立花文穂さんが責任編集・デザイン・製本を手がける雑誌『球体 8号(球体編集)』では、オーブンのなかで羽ばたくように膨らむパンからインスピレーションを受けて制作した『鳩体(きゅうたい)のつくり方』を発表した。「球体と、鳩体と……ダジャレなんですけど(笑)」
─ 表現方法は食べものへと変わっても、「作りたい」という気持ちは、在学中から変わらないように感じました。
そうですね、作りたいです。なるべく食べものに関することで。制作は突然思い立つこともあるし、あたためすぎることもあります(笑)。「モノの命」への葛藤は、まだまだ消化中なんです。どんな風に表現したらいいかなと考え続けていて、最終的には何らかの形でまとめていきたいですが、まだまだなんです(笑)。
でも、流れに身を任すのも面白いなとも思っているので、自分が今後どうなるかわかりません。こういうことをやりたいなって考えていても、思いもよらないことが起こるんです。寄り道しながら進んでいこうかなと思っています。

─ 最後に、学生へのメッセージをお願いします。
学生でいられるって特権ですよね。課題も、自主制作も、はみ出すぐらいでやったらいいなと思っています。お仕事となるといろいろと規制があったりするけど、そうじゃないなら、やりたいことをやったらいい。先生には怒られるかもしれないけど(笑)。でもきっと、その経験は後々「あんなことやったな、こんなことやったな」と何年先にも記憶に残って、制作やお仕事のヒントになると思うし、「あの子、面白かったな」って誰かの記憶にも残って、何かにつながることもあると思うんです。
今は私たちの時代では考えられなかったような職業や働き方がたくさんある。だから、すでに好きなことがある人は、それをどんどんやったらいいなって。そうじゃない人は、悩むのではなく、考えるということをオススメします。どうしたらいい? 自分はどうしたい? と、考えて始めたことには自信もくっついてくると思うから。考えることを、大事にしてみてほしいです。

編集後記:
真っ白く、淡い光が差し込む穏やかなギャラリーのドア一枚向こうにあるtOki dOkiの厨房は、創作のエネルギーに満ち溢れるような真っ赤な空間でした。その対比は、優しく、でもどこかパンクな魂を感じさせる三田さんそのものであるようで。「人とのつながりで世界が広がった」という三田さんご自身が持っている力を、感じられた取材。とっても刺激的な時間を、ありがとうございました。
取材:細野由季恵(10学視/エディター・ディレクター)
ライタープロフィール
札幌出身、東京在住。フリーランスのWEBエディター/ディレクター。
好きなものは鴨せいろ。「おいどん」という猫を飼っている。
撮影:野崎 航正(09学映/写真コース)








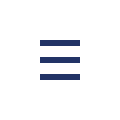













![No.73 池田 咲[健康キャリア実践家]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/ikedasaki_square.jpg)
![No.72 石川 美枝子[ボタニカルアーティスト]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2024/12/ishikawamieko_icatch.jpg)
![No.71 モンゴルマン 斉藤俊一[「あさひの芸術祭」実行委員会代表]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2024/10/00_mongoruman_ichatch.jpg)
![No.70 中川 亮[ゲーム・プロデューサー]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2024/08/nakagawaryo_00_icatch.jpg)
![No.69 池宮城 直美[舞台美術家]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2024/06/ikemiyagi_15.jpg)
![No.68 三田 真由[TOSAKANMURI FOODS主宰/フードクリエーター・パン職人]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2024/05/sanda00.jpg)