齋藤 槙(さいとう・まき)
絵本作家・アトリエうた主宰
(2005年[2004年度]武蔵野美術大学造形学部日本画学科卒業)
1981年東京生まれ。武蔵野美術大学で日本画を学ぶ。動植物を愛し、「こども心」と「物語性」を大切にした作品を貼り絵やステンシルや染めなど、様々な手法で発表している。たくさんの色を重ね、混ぜ合わせることで、深く揺らめくような色を出し、心地よい余白をもたせた作品が多い。
大学在学中から絵本作りをはじめ、著作に『ぺんぎんたいそう』『ながーい はなで なにするの?』(共に福音館書店刊)『おひさま でるよ』(ほるぷ出版刊)などがある。
作家Webサイト:https://saito-maki.com/
うたのアトリエWebサイト:https://uta8.amebaownd.com/
【スライド写真について】
1. 本人ポートレート
2. 貼り絵『シャワー』(2021)/ステンシル『うたごえ』(2018)
3. 絵本『ぺんぎんたいそう(2016、福音館書店))』
4. 自身が運営するうたのアトリエにて
5. ワークショップにて
自分の感覚に、YES・NOを問い続けて
─ ムサビ入学のきっかけを教えてください。
小学生の頃から絵を描くのが好きで、本格的に学びはじめたのは中学1年生の頃。美術の先生に絵を褒められたことを家族に話すと、すぐに近所の絵画教室を探してくれたんです。高校生になり帰り道に立ち寄った本屋で絵本を手に取るうちに「自分は絵本がとても好きだったんだ」と思い出し、絵本作家という職業を強く意識するようになりました。
その後、進路を調べていくと「(絵本を制作するためには)水彩を学ぶ必要があるのでは」と考えたんです。日本画学科の入試で水彩の実技試験があると知り、その美しい余白の表現にも惹かれ、ムサビを受験しました。

― 大学時代に夢中になったことはありますか?
私は鷹の台駅から玉川上水沿いを歩き、ムサビに通っていました。都会育ちだった私にとって、毎日同じ道を歩くことで見える自然の変化は、それまでにない経験でした。季節ごとに同じ木がどう変わるのか、空の色がどう移ろうのか、どんな花が咲くのか。そういった細かな変化を無意識に観察するようになったんです。そうして季節の変化を感じていたある日、小学生の男の子が玉川上水沿いの道を猛ダッシュで駆け抜けていく姿を見かけました。なぜだかその姿がとても印象的で、「この光景を絵本にしたい!」と強く思ったんです。
通学中に自然と向き合った時間や、印象的な出来事に出会った経験が、すべて絵本作りにつながっていると思います。そして、芸術祭で制作・発表したのが和紙に墨で描いた『ぺんぎんたいそう』と、その男の子が森の中を走っていく絵本。このうち『ぺんぎんたいそう』は、卒業後、2016年に福音館書店から発表した作品の原型ともいえるものになりました。

キャプション:当時制作した『ぺんぎんたいそう』
― 齋藤さんの表現スタイルは、どのように確立されましたか?
ムサビでの学びでは、鉱物を砕いて岩絵の具を作る実習が、とても印象に残っています。普段何気なく使っていた絵の具が、実は自然の素材から生まれていることを身をもって感じた経験でした。
鉱物を砕き、すりつぶし、丁寧に仕上げていく過程は、画材を単に「買うもの」としてではなく、「自分で作れるもの」として捉え直すきっかけになりました。どんな時でも、身の回りにある自然の素材を使って絵が描けると知っているだけで、安心感があり、何より楽しい気持ちが生まれるんです。
もうひとつ、卒業してからは貼り絵の技法を用いた絵本を制作していました。アメリカの絵本作家エリック・カールさんの技法にならい、色紙を作って切り貼りする方法を試していたんです。でも背景から順に重ねていくと、どんどんと分厚くなり、最後には絵本に収まりきらなくなってしまいました。それからは「もっとシンプルに、心地よく作業する方法はないか」と考え、重ならないパズルのような貼り絵にすることを思いついたんです。
― 制作の中で感じる“心地よさ”や“安心”を、大切にされているんですね。
大学時代、先生に「色は体質だよ」と言われた言葉が、ずっと心に残っています。そのとき、「自分が心地よいと感じているかどうか」を、自分の身体の感覚で捉えていいんだと気づいたんです。
私は絵を描くとき、色を何層にも重ねたり、少し揺らぎをもたせたりすることが多いのですが、最終的には「ここが心地いいな」と感じたところで筆を止めています。感覚的なことだけれど、それが自分にとって自然な制作の基準になっている気がします。
嬉しい感情も、ちょっと嫌だなと思う感覚も、その都度「今、私はどう感じているか」をちゃんと見つめる。そして、いつも「YES? NO?」と自分に問いかけながら、選んでいく。その判断を他人に委ねてしまった瞬間、自分の人生は少しずつずれていってしまうような気がするんです。だからこそ、私は自分の感覚を信じて、心地よいと感じるほうへ進むようにしています。

― 卒業後は、どのように絵本作家の夢を叶えていったのでしょうか?
私は、本当に運がよかったと思います。大学を卒業した年の10月に、学生時代に制作した絵本を展示する個展を開きました。そこで「絵本作家になりたい」と来場者に伝えていたんです。すると、友人のお母さんが「福音館書店の編集者を知っているから、話してみるね」と声をかけてくれて。
たった6日間の開催期間でしたが、最終日にその編集者さんが来てくださいました。展示していた象の絵を見て、「象の絵本を作ってみたら?」と声をかけてくださったんです。その言葉がきっかけとなり、『ながーい はなで なにするの?』(2019、福音館書店)の制作が始まりました。
もちろん、実際に絵本が出版されるまでには約4年かかりました。でも、「絵本作家としてスタートを切ることができた」という安心感があったので、その期間も焦ることなく、じっくりと向き合うことができたかなと思います。
― 絵本作家になることに、まっすぐに向かって来られたんですね。
高校生のときから、年を重ねてからも思い出せるようなあたたかい記憶になるものを作ることは素敵な仕事だと考えていたんです。だから「本を作る」と決めて以来、ずっとその道を歩んできたように思います。よく「寄り道のない人生ですね」と言われるのですが、これまでずっと、高校生に決めたこの目標に向かって進んできたような気がします。日本画学科ではなく、デザイン科でも絵本作りは学ぶことができたんだということなど、後からわかったこともありましたが(笑)。
― 2年前からは新たに「子どもアーティストのためのプロジェクト“うたのアトリエ”」を立ち上げられています。
絵本作家として展覧会を開いたり、作品を発表したり……これまでいろいろな経験を積ませていただいた今、次にできることはなんだろうなと考え始めました。そこで思い至ったのが、自分がかつて大変だったことを、次の世代に向けてサポートできる場をつくりたいという思いです。
「うたのアトリエ」は、絵画教室のような側面も持ちながら、絵を描くことが好きな子どもたちが、アーティストとしての道や生き方に触れることができる場所でもあります。たとえば、絵本作家やイラストレーターとして活動している人たちが、どんな暮らしをしていて、どんな環境で作品を生み出しているのか。そういったリアルな姿にふれる機会をつくっています。
私自身、日本画を選んだことは決して間違いではなかったと感じています。けれど、もし「ムサビの中でも絵本を学べる学科があるよ」と誰かに教えてもらえていたら、もっと違う選択肢を考えられたかもしれません。
だからこそ、単に技術を学ぶだけでなく、「作ることで生活していくとはどういうことか?」というところまで含めて伝えていく。それが、私が「うたのアトリエ」で目指していることです。

ワークショップの様子。子どもたちと向き合う齋藤さん
― 今後挑戦してみたいことはありますか?
今が挑戦の最中という感覚があります。これまで絵本作家は個人事業主として続けてきましたが、「うたのアトリエ」は法人として運営しています。絵本作家の活動と並行しながら、子ども向けのワークショップなどにも約10年にわたり関わってきましたが、それはあくまで補助的な形でした。今回は、社会的な立場としての“もうひとつの人格”を持ち、継続的にサポートしていくことを意識してスタートしたところです。
子どもでも素晴らしい絵を描くことはありますが、それを「世に出す」ことは、挑戦であると同時にリスクも伴います。評価を受ける場に出るということは、簡単なことではありません。本人にある程度の覚悟がないまま出てしまうと、「評価されなかった=自分には価値がない」と感じてしまう可能性もあるんです。だからこそ、最初の段階ではリスクを最小限に抑えられるように、みんなでひとつの作品を作るなどの工夫をしています。そのうえで、やってみたいという子には、「リスクがあること」「評価を受けるということ」も含めて説明したうえで、挑戦の機会をつくっています。

― 学生へのメッセージをお願いします。
自分の感覚を大切にすることを話しましたが、もしかすると私が一番伝えたいことかもしれません。「好き・嫌い」、「心地よい・心地悪い」、そういった自分の中で起きている感情に対して、フラットな目線で向き合う。学生のうちは時間があるからこそ、あまり突き詰めすぎると苦しくなってしまうこともあります。ときには逃げてもいいと思うのですが、そういった感覚に素直になってみると、いずれ自分にとっての大きな指針になっていくような気がするんです。
私自身も、結局は「心地よい」と感じる方に進んできました。それが結果的に、今の自分につながっていると思います。もし何か迷っていることがあるなら、まずは「今、自分がどう感じているか」に目を向けてみると、何かが見えてくるかもしれません。
取材:細野由季恵(10学視/エディター・ディレクター)
ライタープロフィール
札幌出身、東京在住。フリーランスのWEBエディター/ディレクター。
好きなものは鴨せいろ。「おいどん」という猫を飼っている。
撮影:野崎 航正(09学映/写真コース)





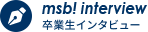
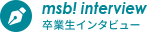

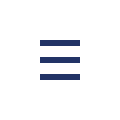










![No.73 池田 咲[健康キャリア実践家]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/ikedasaki_square.jpg)
![No.72 石川 美枝子[ボタニカルアーティスト]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2024/12/ishikawamieko_icatch.jpg)
![No.71 モンゴルマン 斉藤俊一[「あさひの芸術祭」実行委員会代表]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2024/10/00_mongoruman_ichatch.jpg)
![No.70 中川 亮[ゲーム・プロデューサー]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2024/08/nakagawaryo_00_icatch.jpg)
![No.69 池宮城 直美[舞台美術家]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2024/06/ikemiyagi_15.jpg)
![No.68 三田 真由[TOSAKANMURI FOODS主宰/フードクリエーター・パン職人]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2024/05/sanda00.jpg)
![No.67 谷 充代 [執筆家]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2023/09/tani0.jpg)